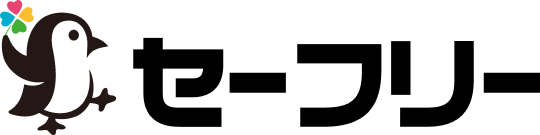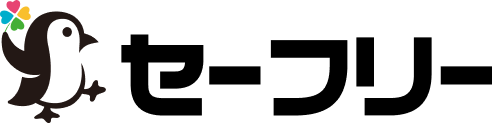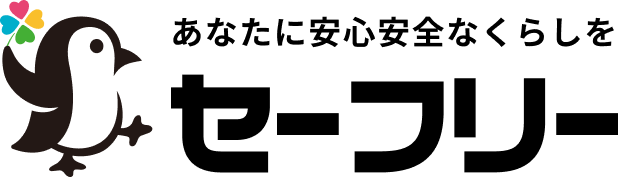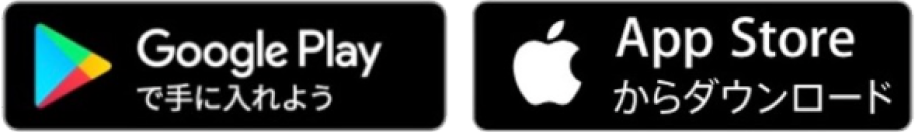2024.09.20 2025.04.11
この記事では、犬が噛む原因や理由を理解し、効果的なしつけ方法や改善策を紹介します。
また飼い主を噛む、家具を噛む、唸る行動についても詳しく解説し、子犬の甘噛みの対処法も含めてお伝えします。
愛犬が噛んでしまうことにお悩みの方は、ぜひしつけの参考にしてください。
PR
トレーニング・しつけ
今週No.1おすすめ優良業者!!

ほめほめホーム
犬の保育園ほめほめホームは横浜市内の自宅店舗で犬の保育園を運営しています。「叱らないしつけ」で、愛犬も飼い主様も楽しく学ぶことができます。飼い主様も「褒め上手」になり、愛犬との絆を深めましょう。遠方の方向けに、オンラインで「犬のしつけ方教室」も開催しているのでぜひご検討ください。
対応エリア神奈川県
目次
噛み癖を治すためのしつけ方法

愛犬が噛んでしまう場合でも、適切なしつけやトレーニングで噛み癖を改善することができます。
ここでは以下のようなシチュエーションごとの、しつけ方法や対策を紹介します。
- 飼い主を噛む犬へのしつけ方法
- 他の人を噛んでしまう犬のしつけ方法
- ほかの犬を噛む場合のしつけ方法
- 唸って噛みつこうとする犬へのしつけや対策
- 適切な社会化を行う
具体的に犬が噛むときのしつけ方法・対策を解説していきます。
飼い主を噛む犬へのしつけ方法
飼い主を噛む犬への対処は、根気強さと一貫性がポイントです。
まず、噛まれそうになったら、すばやく手を引っ込め、「痛い」とはっきり伝えましょう。これで、犬に対して自分の良くないことなのだと気づかせることができます。
噛む行為には反応せず、そっと離れることも効果的です。反応しないことでその行為が楽しいものではないと理解してもらいます。
代わりに、おもちゃを差し出して噛む対象を切り替えるのもおすすめです。言うことを聞いてくれたときは、たくさん褒めて好きなおやつをあげることで、いい行動を学習させます。
他の人を噛んでしまう犬のしつけ方法
他の人を噛んでしまう犬への対応は、早めの取り組みと上手なしつけがカギとなります。
まず、飼い犬が人に近づくシチュエーションの時は、必ず短めのリードでしっかり管理をしましょう。
もしも飛びつきそうになったときは、リードを引いて注意を引くことで噛むのを防ぎます。
可能であれば、人と触れ合う機会を少しずつ増やし、楽しい思い出を作ることが大切です。その時に犬が落ち着いていられたときは、たくさん褒めてお気に入りのおやつをあげてください。
警戒心が強い犬の場合は、無理に人と関わらせるのではなく、ゆっくりと距離を縮めていきます。
また、「お座り」や「伏せ」などの基本的なしつけとコマンドを身につけさせると、人と接する場面でもうまくコントロールできるようになります。
ほかの犬を噛む場合のしつけ方法
他の犬を噛む場合、まずは社会化不足が原因であることが多いです。
子犬の頃に十分な社会化を行わなかった犬は、他の犬との接触に慣れておらず、緊張や不安から噛んでしまうことがあります。
このような場合は、じょじょに他の犬と接する機会を増やし、慣れる練習を行いましょう。興奮しすぎることが原因で噛む場合もあります。
遊びの中で興奮が高まると、加減を忘れて噛んでしまうことがあるため、遊びが激しくなる前に一旦止め、落ち着かせる時間を作ることが大切です。
リードの管理も重要です。散歩中に他の犬を見かけたら、リードを短めに持ち、相手との距離を保つのがベストです。
吠える・近づかないで通り過ぎることができたら、すぐに褒めてご褒美をあげることで、正しい行動を学習させます。
唸って噛みつこうとする犬へのしつけや対策
犬が唸って噛みつこうとする行動は、怖がっていたり不安を感じていたりすることが多いです。
こういった行動には、上手なしつけと犬が過ごしやすい環境づくりが大切です。知らない人や他の犬を見て唸るようなら、社会化が足りていない可能性があります。
唸って噛む行動を減らすには、少しずつ新しいことを経験させて、それを楽しい思い出にしていくのが効果的です。また、唸り始めたら無理に近づかないで、犬がホッとできる距離を保つのも大切なポイントです。
適切な社会化を行う
適切な社会化を行うには、子犬のうちからさまざまな人や動物、環境に触れさせることが大切です。散歩や犬の幼稚園、しつけ教室などに参加させるのも効果的でしょう。
ただし、無理に慣れさせようとするのではなく、犬のペースに合わせて徐々に経験を積ませていくことが重要です。このように、適切な社会化は噛み癖の予防にも繋がる重要な要素なのです。
噛み癖のしつけの前に日常ケアと環境作り

犬が噛んでしまうのをやめさせるには、しつけをする前に日々の生活や環境を整えることも大切です。
愛犬にとってストレスの少ない生活環境を提供する
愛犬にとってストレスの少ない生活環境を提供することは、噛み癖の改善に大きく役立ちます。まず、犬が安心して過ごせる静かな場所を確保しましょう。
- コミュニケーションの時間をとる
- 生活リズムを整える
- 家族全員が一貫した態度で接す
愛犬とのコミュニケーションの時間も非常に重要です。毎日の散歩や遊びの時間を設けることで、ストレスの発散につながります。
食事や水、トイレの場所を一定に保ち、生活リズムを整えることも大切です。急な環境変化は犬にとってストレスになるため、避けるようにしましょう。
家族全員が一貫した態度で接することも重要です。ルールを統一し、愛情を持って接することで、犬は安心感を得られます。
このような環境づくりが、噛み癖の改善につながるのです。
定期的な運動と適切な刺激を与えてあげる
定期的な運動と適切な刺激を与えることは、犬の噛み癖改善に効果的です。毎日の散歩は、ストレス発散と体力消費に重要な役割を果たします。
散歩の時間や距離は、犬種や年齢に応じて調整しましょう。
室内でも、ボール遊びやフリスビーなど、犬が楽しめる遊びを取り入れると良いでしょう。また、知育玩具を活用することで、犬の知的好奇心を満たすことができます。
運動や遊びの後は、十分な休息時間を設けることも大切です。適度な運動と刺激、そして十分な休息のバランスを取ることで、犬のストレスを軽減し、噛み癖の改善につながります。
犬が噛む理由を理解することがしつけの第一歩

犬が噛む行動にはさまざまな理由があります。効果的なしつけを行うためには、まずその理由を理解することが重要です。
ここでは、犬が噛む主な理由について解説していきます。
飼い主を噛む理由
犬が飼い主を噛む理由には、いくつかのパターンがあります。
遊びやコミュニケーションの延長として噛むことが多く、特に子犬は遊びの中で手や足を噛んでしまうことがあります。
犬にとって噛むことは自然な行動ですが、力加減がわからないため、意図せず飼い主に痛みを与えてしまうことも珍しくないのです。
また、自己主張や要求を伝える手段として飼い主を噛むこともあります。
たとえば、食べ物が欲しい、遊んでほしいなど、要求を満たしてもらおうとして噛む子も。ほかにも不安やストレスを感じた際、飼い主に噛みつくことでその感情を発散することもあります。
なかには、過去のトラウマや不適切な社会化(環境適応トレーニング)が原因で噛む犬もいるでしょう。愛犬の行動をよく観察し、噛む理由を適切に見極めることが大切です。
来客に噛みついてしまう理由
犬が来客に噛みついてしまう理由には、警戒心や縄張り意識が関係していることが多いです。
犬は自分の家や飼い主を守ろうとする本能があり、見知らぬ人が家に入ってくると、危険を感じて攻撃的な行動を取ってしまうことがあります。
散歩中、通りすがりの人に噛みつこうとしてしまうのも、同様の理由からです。
また子犬の時期に他の人と接する機会が少ないと、成犬になってからも人に対して警戒心を抱きやすくなります。
人見知りが激しく、恐怖心から防衛行動として噛むことも考えられるのです。
ほかの犬を噛む理由
散歩中にほかの犬を噛む理由として、強い恐怖心や不安が挙げられます。犬は、他の犬と接触することに対して恐れを感じると、防衛反応として噛むことがあるのです。
この場合、他の犬が近づく前に吠えたり唸ったりするサインが見られることが多く、恐怖や緊張が噛みつきという攻撃的な行動につながります。
幼少期に十分な社会化が行われていない犬は、他の犬との接触に慣れておらず、コミュニケーションの取り方がわからず噛むことがあります。
噛む行動と唸る行動の関係
犬が唸るのは、警戒心や不安を表現するサインであり、唸りが噛む行動に発展することがあります。唸ることで相手に対し「これ以上近づかないでほしい」という警告を発しているのです。
唸りを無視して接触を続けると、犬は最終手段として噛むことがあります。
また、犬が唸るときは自分の縄張りや資源(食べ物やおもちゃ)を守ろうとしている場合もあります。
この場合、唸りや噛む行動は防衛的な意味合いが強いです。唸りを早期に認識し、その原因に対応することが大切です。
犬が唸る際は、そのまま噛む行動に移らないよう、飼い主が冷静に状況を見極め、必要に応じてしつけやトレーニングを進めましょう。
社会化期の社会化不足も多く影響する
犬が噛む理由の一つに、社会化不足などもあげられます。社会化とは、犬が人間や他の動物、さまざまな環境に適応するための環境適応トレーニングであり、重要な学習過程です。
特に生後3週間から12週間(または~16週間)までの期間(社会化期)が、犬の社会化にとって最も重要な時期とされています。
この時期に適切な経験を積むことで、犬は将来的に安定した行動を取れるようになるのです。
社会化が不足すると、犬は新しい状況や刺激に対して不安や恐怖を感じやすくなってしまいます。そのため、見知らぬ人や動物に対して攻撃的な反応を示したり、過度に警戒心を抱いたりすることがあるのです。
子犬の甘噛みをやめさせる方法

子犬の甘噛みをやめさせるには、一貫した対応と根気強いしつけが必要です。
甘噛みは子犬にとって自然な行動ですが、放置すると大人になっても続く可能性があり、深刻な問題に発展する恐れがあります。
甘噛みをしたときは低い声で「痛い!」「ダメ!」と叱り、噛んではいけないことを教えましょう。同時に、噛んでもよいおもちゃを与え、適切な噛む対象を学ばせます。
また、甘噛みをしたら遊びを中断し、無視することも効果的です。反応しないことで、噛むと楽しい時間が終わることを学習させます。
しつけは毎日の積み重ねが大切です。根気強く続けることで、子犬は徐々に甘噛みをやめ、適切な行動を身につけていきます。
愛犬の噛み癖のしつけはトレーナーに相談がおすすめ!
愛犬が噛んでしまわないようしつけをするためには、なぜ噛んでしまうのかその理由を理解することがポイントです。
犬の気持ちを理解したうえで適切なしつけを行うことにより、噛み癖を効果的に改善できます。
深刻な犬の噛み癖の悩みは、しつけの専門家やドッグトレーナーに相談するのがおすすめです。
セーフリーには噛み癖改善の相談に応じてくれるトレーナーが登録しています。
愛犬の噛み癖やしつけに対応しているトレーナーをお探しの際は、ぜひセーフリーをご活用下さい。
>>>ドッグトレーナーや犬のしつけ教室を今すぐセーフリーで検索
- 愛犬の噛み癖をやめさせたい
- なんで噛んでしまうのか理由を知りたい
- 他の人が噛まれてケガをしないか心配
- 今すぐドッグトレーナーに相談!