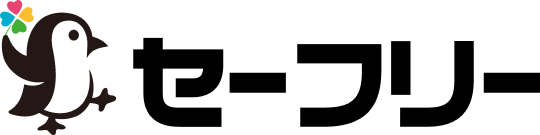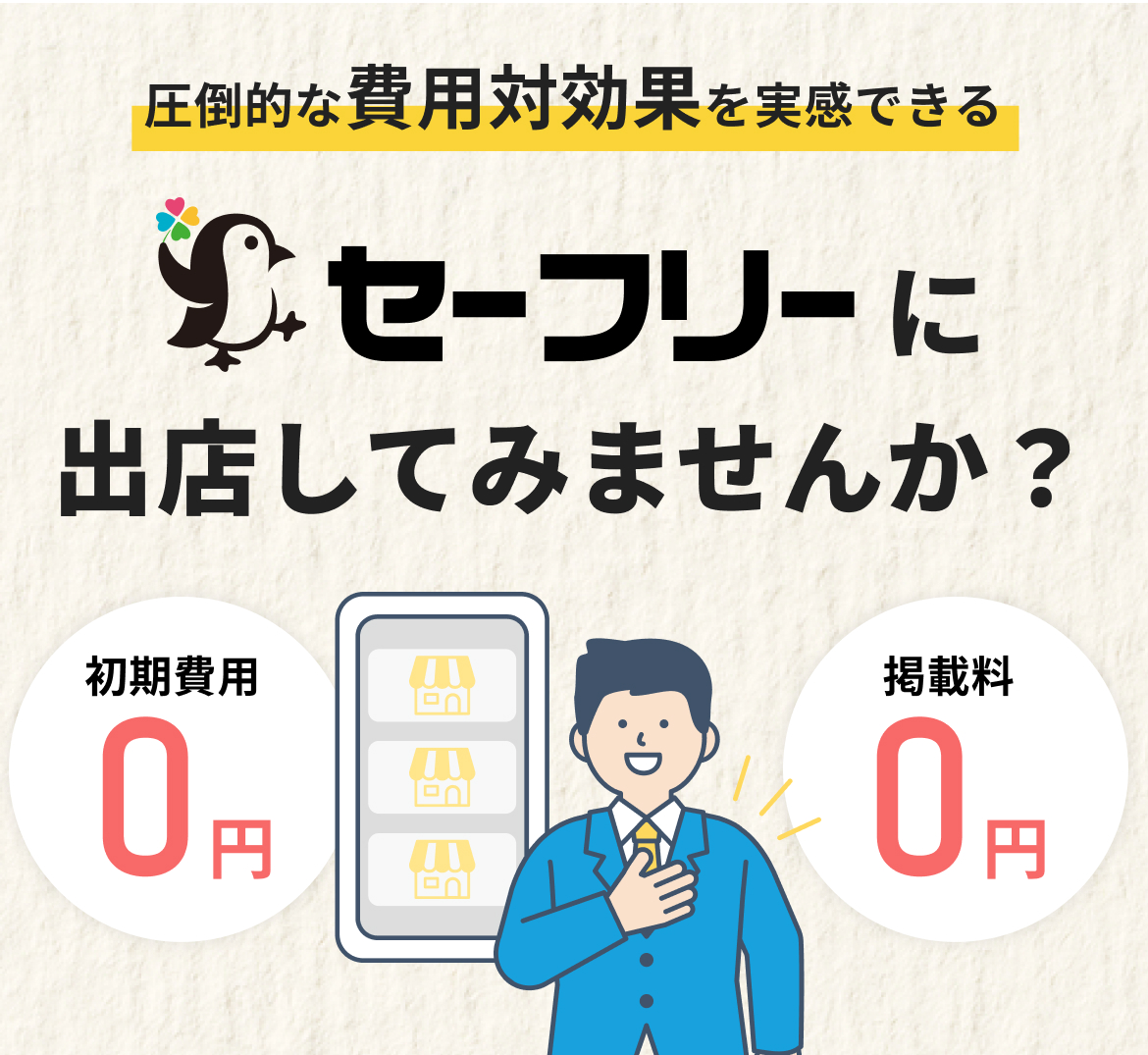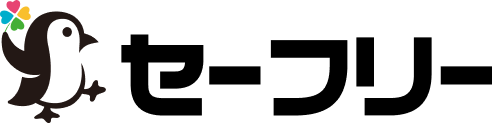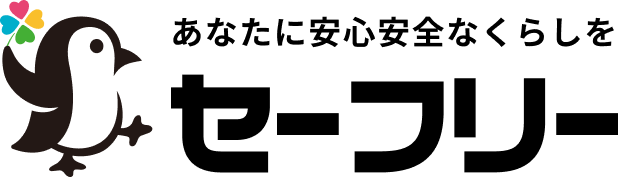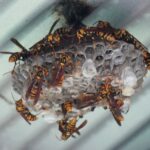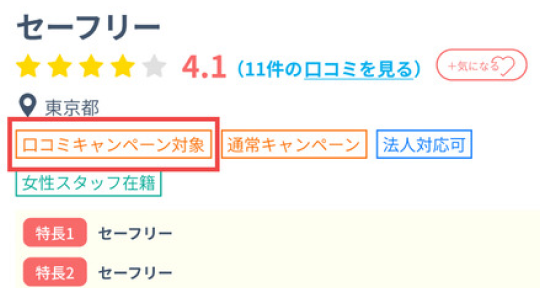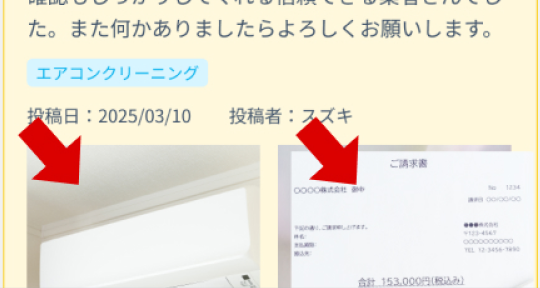2025.03.17 2025.06.30
ペットロスを乗り越える方法をご紹介します。
家族同然のペットを失った時、飼い主の多くが深い喪失感を味わい、中には数カ月もペットロス症状に苦しむ方も。症状に個人差があるとはいえ、ペットロスを乗り越えるためには時間が必要です。
この記事では、ペットロスの過程や長引く要因について詳しく解説し、乗り越えるための具体的な方法を解説していきます。
目次
ペットロスで引き起こされる悲しみの過程

ペットロスで引き起こされる悲しみの過程についてご紹介します。
ペットロスとは、ペットと死別することで飼い主が味わう喪失感を表す言葉で、近年では生活環境の変化に伴い、ペットロスになる方がより多い傾向があります。
ペットロスには、いくつかの悲しみの過程があるとされており、その段階を経て心が回復していくようです。これは一般的に「グリーフケア」として知られているもの。
このグリーフの過程には、衝撃期、悲痛期、回復期、再生期の4つの段階があり、順番に超えていくケースがしばしば。それぞれの過程をクリックすると、過程ごとの乗り越え方の情報に移行できます。
〇衝撃期
急に直面したペットの死を受け入れられず、現実として事実を受け止められない時期です。「信じられない」、もしくは「信じたくない」という感情が入り乱れ、悲しいのに涙が出ないという方もいらっしゃいます。
〇悲痛期
少しずつペットがいなくなった現実を理解し、深い悲しみや喪失感に襲われる時期です。ペットとの思い出が蘇り、涙が止まらなくなることも少なくありません。
特に、いつもペットがいた場所や時間に虚しさを感じ、強い孤独感に襲われ、感情が不安定になりやすい特徴があります。
〇回復期
現実を自分なりに受け止め、徐々に日常生活に戻り始める時期です。
ペットとの思い出を涙なく思い出すことも可能になり、気持ちの安定が日常化しつつあります。ただ、ふとした瞬間にペットを思い出して悲しくなることもありますが、この感情の波を超えることが大切。
〇再生期
ペットと過ごした時間を良い思い出として大切にしながら、前向きに生活できるようになる時期です。ほぼ支障なく日常生活を送ることができるようになるでしょう。
中には、新たなペットを迎え入れることを考慮できるまで回復するケースも少なくありません。
ペットロス|衝撃期の乗り越え方

ペットロスの衝撃期の乗り越え方をご紹介します。
ペットロスの初期段階である衝撃期ですが、この時期にはペットがいなくなった事実を受け止めることができず、不安定な感情が入り乱れます。「気持ちの整理がつかない」とよく言いますが、まさにその状態。
どのように乗り越えたらよいのか、具体的な方法を解説していきます。
葬儀をしてきちんとお別れをする
ペットが亡くなったら、気持ちを整理して現実を受け入れるためにも、まずはきちんとお別れをしましょう。
人間の場合と同じように、葬儀や供養の儀式をすることで現実を目の当たりにして、気持ちの整理をつきやすくするのです。
「受け入れたくない」と拒否してしまいがちですが、ペットの尊厳を保つためにもきちんと葬儀を行ってください。感情が混乱しても、お別れの儀式をして安らかに眠らせてあげましょう。
さらに詳しく知りたい方はこちら
最愛のペットの供養方法を紹介!供養のための法要の種類も詳しく解説
2025.02.26 2025.02.26
家族や友人と悲しみを共有する
ペットがいなくなってしまった時、悲しいのは自分一人ではありません。一人で悲しみの感情を抱え込まず、周囲の人と気持ちを分かち合うことが助けになります。
家族や親しい友人と一緒に、ペットとの思い出を語り合いながら感情を共有することで、少しずつ気持ちが落ち着きを取り戻し、心が整理されるでしょう。
また、同じようにペットロスを経験した人と話すことで、少しずつ現実を受け入れる準備ができます。
思い出を振り返る
ペットの生前の写真や動画を見返し、楽しかった時間を思い出すことも心の整理につながります。
ペットとの楽しい思い出を振り返ることで、深い悲しみや喪失感の中にも温かい気持ちを感じることができるでしょう。
ペットの写真や動画を見たり、日記を書いたりすることで、ペットが自分の人生にどれだけの喜びを与えてくれたかを再確認でき、感謝の気持ちと共に丁寧に送り出してあげたいと感じるはずです。
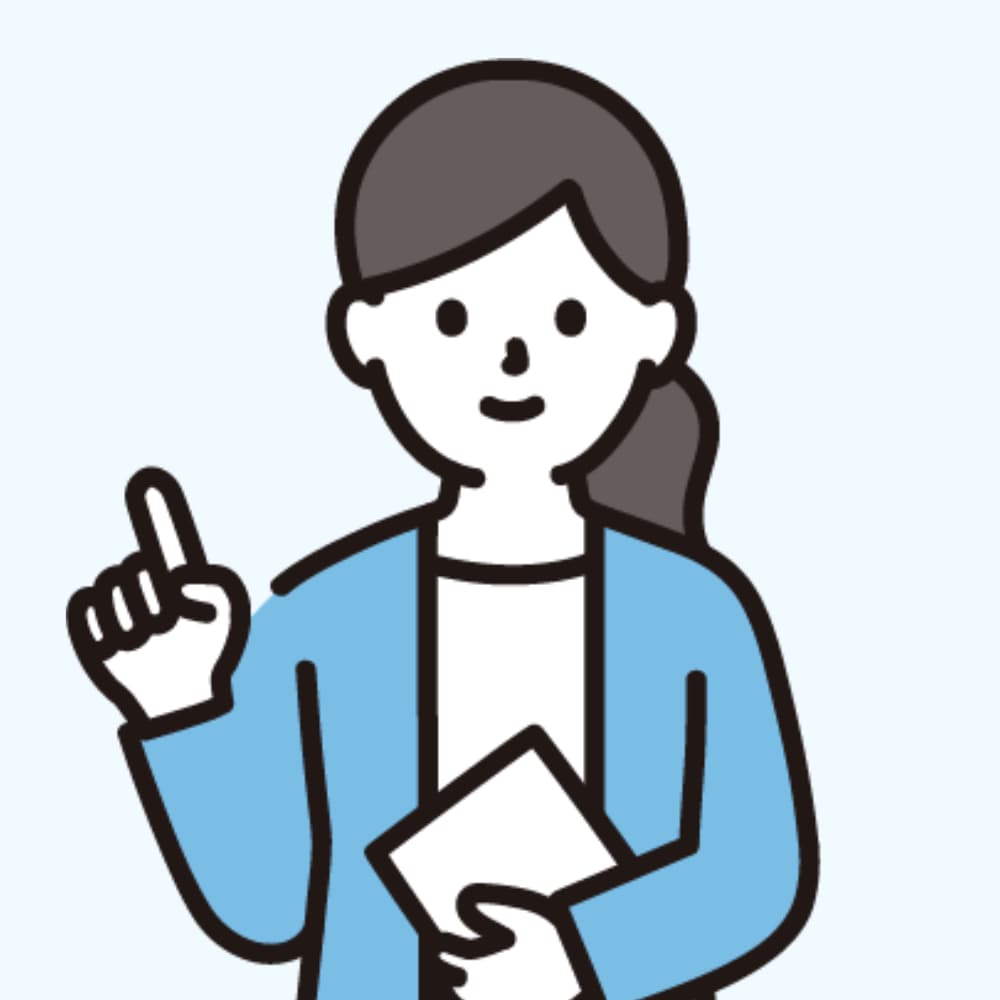
セーフリーWEB担当
>コンテンツパートナーズ合同会社を見てみる
ペットロス|悲痛期の乗り越え方

ペットロスの悲痛期の乗り越え方をご紹介します。
ペットロスの第2段階と言われている悲痛期ですが、この時期は深い悲しみや喪失感に襲われるケースが多く、感情も不安定になりがち。どのように対応できるのか、具体的に解説していきます。
カウンセリングを受ける
感情が不安定になって日常生活に支障が出やすい悲痛期は、とにかく無理をせず、自分をコントロールできないと感じたら、ペットロス専門のカウンセリングを受けてください。
多くの方は、悲痛期に入るとペットを失った現実が深く突き刺さり、心が大きく揺れ動くように感じます。自分で上手く対処する方もいらっしゃいますが、他人に気持ちを聞いてもらうことが解決策になる場合も。
近年では、通常のメンタルヘルスクリニックに加え、ペットロスに特化したカウンセリングを行っている機関もありますので、話を聞いてもらうだけでも検討してみましょう。
気持ちを抑えず泣きたいときは泣く
ペットを失って悲しい気持ちになることは、至極当たり前の感情です。また、その感情を無理に抑え込む必要もありません。
涙を流して悲しみの感情をさらけ出すことは、心の回復に繋がる必要なプロセスのひとつです。泣きたいときは思いっきり泣き、悲しみをしっかりと自覚することが回復への第一歩なのです。
よく「泣くとスッキリする」と言いますが、まさにその通りで涙を流すことで気持ちが落ち着き、心の整理がしやすくなるでしょう。
同じような経験をしている人と話す
自分と同じようにペットロスを経験した人と話すことで、つらい時期を乗り越えることもできます。
ありのままのつらい気持ちを共有できる相手がいれば、この感情は自分だけではないと実感し、不思議と心が軽くなるかもしれません。
インターネット上の掲示板やSNSなどで、ペットロスに関するコミュニティを探してみるのも良い方法です。
虹の橋の詩を読む
「虹の橋」という詩を読むことも癒しになる方法のひとつです。
この虹の橋という詩は、亡くなったペットが天国で飼い主を待っているという内容の詩で、多くのペット愛好家の間で広く知られています。
この詩を読むと、ペットを失って悲しい気持ちに変わりはありませんが、温かな気持ちも同時に感じることができます。ペットがいつまでも心の中で生き続けるという希望を感じることができるでしょう。
ペットロス|回復期の乗り越え方

ペットロスの回復期の乗り越え方についてご紹介します。
ペットロスの第3段階と言われる回復期ですが、この時期は少しずつ悲しみが和らぎ、前のような日常生活を取り戻しつつある段階です。時に感情が不安定になりますが、そんな時は自分なりの対策が必要。
具体的にできる乗り越え方を解説します。
適度に外出するなど、気分転換をする
少しずつ悲しみが和らいできたこの時期には、散歩や旅行などを通じて気分転換を図ることが大切です。
一般的にペットロスの回復期は、少しずつ日常生活を取り戻せるようになるケースが多く、忙しく過ごしていたり、どこかに出掛けた時には心の痛みが和らいでいることに気付きます。
思い出の中だけに浸らず、外に出て新鮮な空気を吸ったり、自然の中を散歩したりすることで、気持ちをリフレッシュさせてください。
趣味や好きなことをして楽しむ
ペットを失ったことで空いた時間を、自分の好きなことに没頭する時間に変えてみるのはいかがですか?
ペットを失った喪失感を埋めるために、今までできなかった興味があることに取り組んでみたり、趣味に取り組む時間を増やすなど、夢中になれる他のものを探すのです。
趣味がないにしても、好きな音楽を聴いたり、映画を見たりする時間を取り分けることで、ペットのことだけを考える時間を少なくしていき、心を軽くしてあげましょう。
ペットロス|再生期の乗り越え方

ペットロスの再生期の乗り越え方をご紹介します。
ペットロスの最終段階となる再生期ですが、この時期はペットと過ごした時間が良い思い出になり、少しずつ前向きに生活できるようになっていきます。新しい段階に踏み込むケースもあり、回復はもう目の前。
どんな風に気持ちを切り替えることができるのか、乗り越え方を詳しく解説します。
思い出の品を飾る
日常生活が送れるようになっている再生期には、ペットとの思い出を笑顔で話せているでしょう。ペットの写真や動画、遺品を大切にして、思い出を形にすることで心を落ち着かせることができます。
ペットの写真を家の中に飾ったり、アルバムを作ったりしてみてください。思い出の品が手元にあることで、悲しみだけでなく、楽しかった記憶も蘇ってきて幸せな気持ちになれます。
この頃には、定期的な供養の儀式にも気持ちが向いていると思いますので、お参りしたり、供養祭に出掛けることもできます。
新しいペットを迎え入れる
ペットロスの再生期に入ると、中には新たなペットを迎え入れることを考え始める方も。このタイミングは人それぞれですが、新しいペットがいることで悲しみが和らぐと感じる方がいらっしゃるのも事実。
ただ、新しいペットのお迎えのタイミングは、人に勧められたからなど無理に決断するものではありません。自身の気持ちに従って、気持ちが落ち着いてからでも遅くはないでしょう。
ペットロスを乗り越えるポイント

ペットロスを乗り越えるポイントをご紹介します。
回復に時間がかかるペットロスの症状ですが、重症化させずに上手に乗り越えるには、幾つかのポイントをおさえておく必要があるでしょう。
ペットロスと上手に付き合いながら、回復するポイントを解説します。
衝撃期は生きているときにも訪れる
感情が不安定で、とにかく現実として受け入れられないという「衝撃期」は、ペットが生きている時でさえ感じるものです。
愛するペットの病気や老化を目の当たりにした時、衝撃期のようなショックに近い感情が湧くことがあります。病気や老化の進行を見て、すでに喪失感を抱くのです。
ですから事前に心の準備をしておくなら、いざという時も上手に乗り越えていけるでしょう。
無理に治そうと焦らない
ペットロスからの回復には、とにかく長い時間がかかります。人によっては短期間の場合もありますが、ペットと過ごした時間が長かったり、依存度が高かった場合は特に時間が必要でしょう。
無理に早く元気になろうとすると、気持ちが追い付かず余計に症状が悪化することがあります。ペットロスは時間をかけて向き合うべきものですので、焦りは禁物。
自分のペースでゆっくりと受け入れることが大切です。
自分の心の動きを否定しない
人によって悲しみの度合いや深さ、表現方法は様々です。「もう立ち直らなければならない」と焦る必要はありません。悲しみの気持ちに逆らわずに、自分の感情に素直になりましょう。
ペットロスの感情を否定せず、ありのままに受け止めることが回復への第一歩となります。
「~しないといけない」と自分に強要しない
とかく日本人は、「しないといけない」や「してはいけない」などの制限を自分に課せがちです。「泣いてはいけない」、「早く立ち直らなければいけない」、「新しくペット迎えなければいけない」など強要はやめましょう。
自分の状況を悲しみの過程で区切って、行動を制限するのは逆効果です。現時点で十分につらい思いをしているのですから、まずは自身の気持ちを最優先して、無理せず自分のペースで進んでください。
ペットロスには一般的な乗り越え方がありますが、人それぞれ悲しみ方は異なるのですから、それを厳密に守る必要はありません。
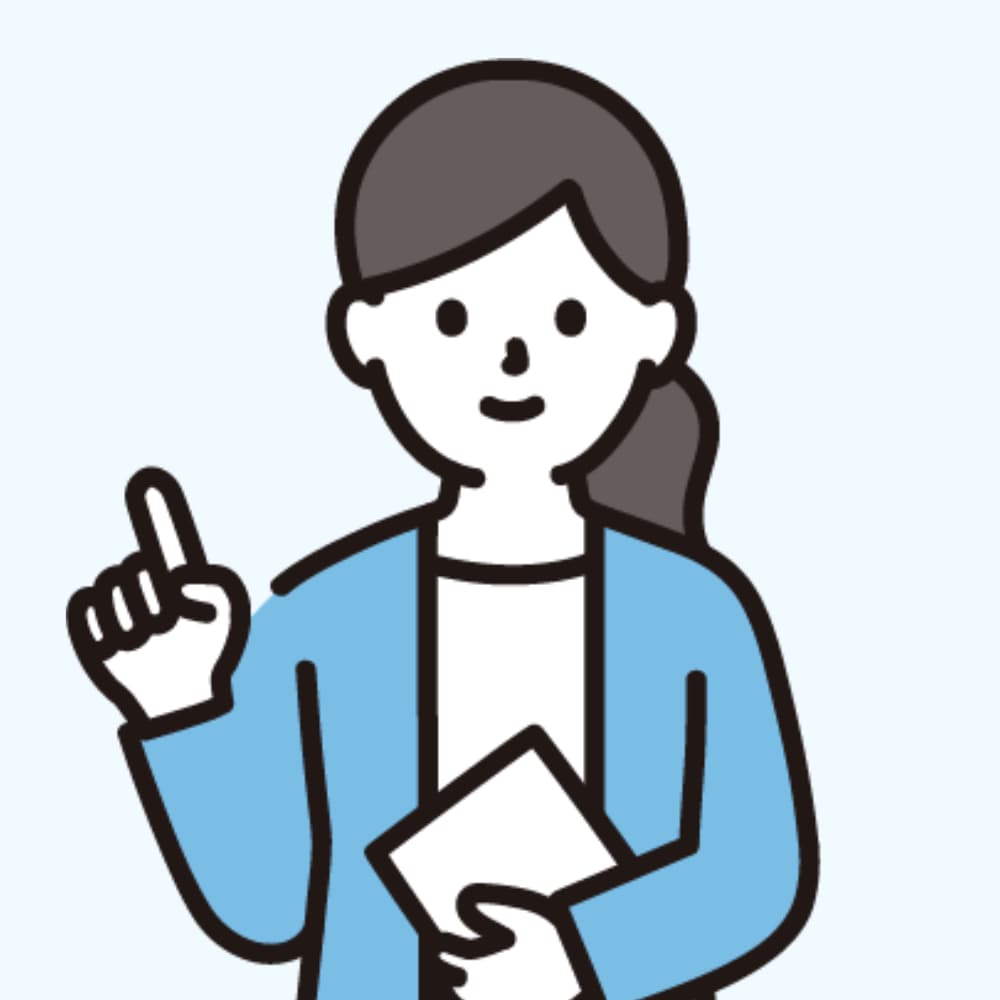
セーフリーWEB担当
>コンテンツパートナーズ合同会社を見てみる
ペットロスの期間と長引く要因

ペットロスの期間と長引く要因をご紹介します。
一般的にペットロスの症状が続く期間の平均は、数カ月~1年程度と言われていますが、実際に回復するまでの詳細な期間は個人によって異なります。場合によっては1年以上症状に苦しむケースも。
以下のような要因によって、ペットロスの期間が長引く可能性があります。
悲しみを誤魔化している
悲しみの感情を誤魔化して無理に気持ちを隠すと、かえってペットロスが長引くことがあります。上手く表現できないだけという場合もありますが、気持ちを誤魔化すことは得策ではありません。
声を出して泣いたり、つらい時には無理をしないなど、気持ちを素直に受け入れて悲しみを自覚しましょう。
自責や後悔が強い
亡くなったペットに対して自責や後悔の念が強い場合、ペットロスの症状が長引くケースがあります。
特に、突然の事故や病気が原因でペットが亡くなった場合、「もっとこうしてあげればよかった」と強く後悔することで、気持ちが整理できなくなることがあるでしょう。
突然死別した
事故や急病などで、予期していなかった時に突然別れが訪れると、気持ちの整理がつきにくくなります。頭の片隅ではペットとの別れは突然だとわかっていても、気持ちが付いていかないのです。
ペットロスの感情は、悲しみだけではなく、驚きやショック、後悔など様々な感情が入り乱れて発症するものです。突然の出来事に戸惑い、受け入れられないまま引きずるケースも少なくありません。
悲しみを共有できる相手がいない
ペットを失った悲しみを分かち合える相手がいないと、ペットロスが長引く可能性があります。家族や友人などに話そうとしても、ペットに関する価値観が異なり、思ったように感情移入してもらえないケースも。
また自分の感情をさらけ出すことが苦手な人の場合、誰かにつらい気持ちを話せないので、上手く感情を発散できずに症状が深刻化する場合もあります。
さらに詳しく知りたい方はこちら
ペットロス時に見られる症状をご紹介!辛い時の乗り越え方を解説
2025.03.30 2025.05.22
同居のペットもペットロスになることがある

ペットロスになるのは、飼い主だけとは限りません。飼っているペット同士が深い絆を持っていた場合、生き残ったペットもペットロスを経験することがあります。
特に同じ属種のペット、犬同士や猫同士、インコ同士などは、仲間がいなくなったことによる喪失感を感じ、人間のペットロスと同じような症状が見られる場合も。
以下のような症状がペットに見られるなら、十分な注意とケアが必要です。
- 以前より鳴くようになった
- 食欲が落ちている
- 遊ばなくなった
- ずっと寝ている
- 粗相が増えた
- 飼い主への執着がひどくなった
同居しているペットも飼い主と同様に、仲間を失うことでペットロスを経験し、心と体に不調をきたす場合があります。亡くなったペットのことだけでなく、残されたペットのケアも忘れないようにしましょう。
さらに詳しく知りたい方はこちら
2025.03.27 2025.06.30
ペットロスは焦らずにゆっくり乗り越えよう!
ペットロスを乗り越える方法をご紹介しました。
ペットを失った時には、飼い主の多くが深い喪失感を味わい、数カ月以上もペットロス症状に苦しむ方もいらっしゃいます。しかもペットロスに苦しむのは飼い主だけでなく、同居のペットも経験する可能性も。
ですが、ペットロスを乗り越えるためにはある程度の時間が必要で、焦りや無理は症状を長引かせる原因になりますので厳禁です。気持ちを抑えず、自分のペースで回復を目指しましょう。
ペットロスを上手に乗り越える方法の中には、ペットを丁寧に供養することも含まれます。ペットの葬儀や供養でお困りなら、ぜひ「セーフリー」をご活用ください。
セーフリーなら、エリア別にペットの葬儀場やお見送りサービスを行う事業者を検索することができ、条件や希望をまとめて比較することが可能!スムーズにペットロスを乗り越えるためにも、ぜひご活用ください。
- ペットを丁寧に見送ってあげたい
- 急な出来事でどうすべきか分からない
- 葬儀や供養をサポートしてほしい
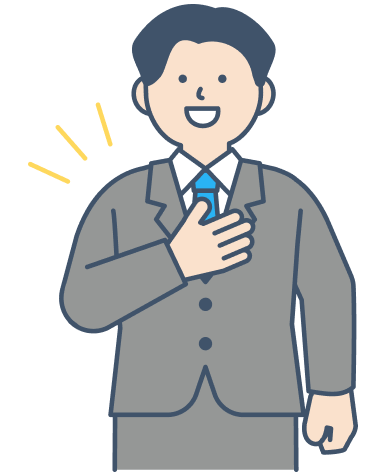
急なペットのお見送りはとにかく不安
そんな時はプロの業者に相談!
ペットロスに関するよくある質問
-
Q. 友人がペットロスなのですが、どのようにサポートしたらいいですか?
A.ペットロスの人に対してしてあげられることは、とにかく話を聞いて、共感してあげることです。相手が話そうとしている時には、静かに受け入れてあげてください。
ペットロスには幾つかの過程がありますので、アドバイスなどは相手のタイミングと合わない可能性があるので、かなり回復するまでは極力避けたほうがよいでしょう。
-
Q. どんな人がペットロスになりやすいですか?
A.ペットに執着がある方や周りとあまり関わりがない人は、ペットへの依存度が高く、心の支えとなっているぶん、亡くした時の喪失感がすさまじいと言われます。
また自身が子どもの頃から一緒に成長したペットは、長期間一緒に過ごし、兄弟のような感覚の方も多いため、ペットロスになりやすいと言われています。
-
Q. ペットロスの症状が悪化するとどうなりますか?
A.通常、ペットロスの症状は何カ月程度、もしくは1年以内で治まってくるケースが多いのですが、感情をうまく吐き出せずに長期化する方もいらっしゃいます。また深刻化して、うつの発症や不安障害などに移行することも。
眠れない、食事がとれない、気分が落ち込んで何もできないという症状が半年以上続く場合は、医療機関やメンタルクリニックの受診を検討することをおすすめします。