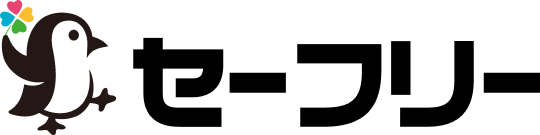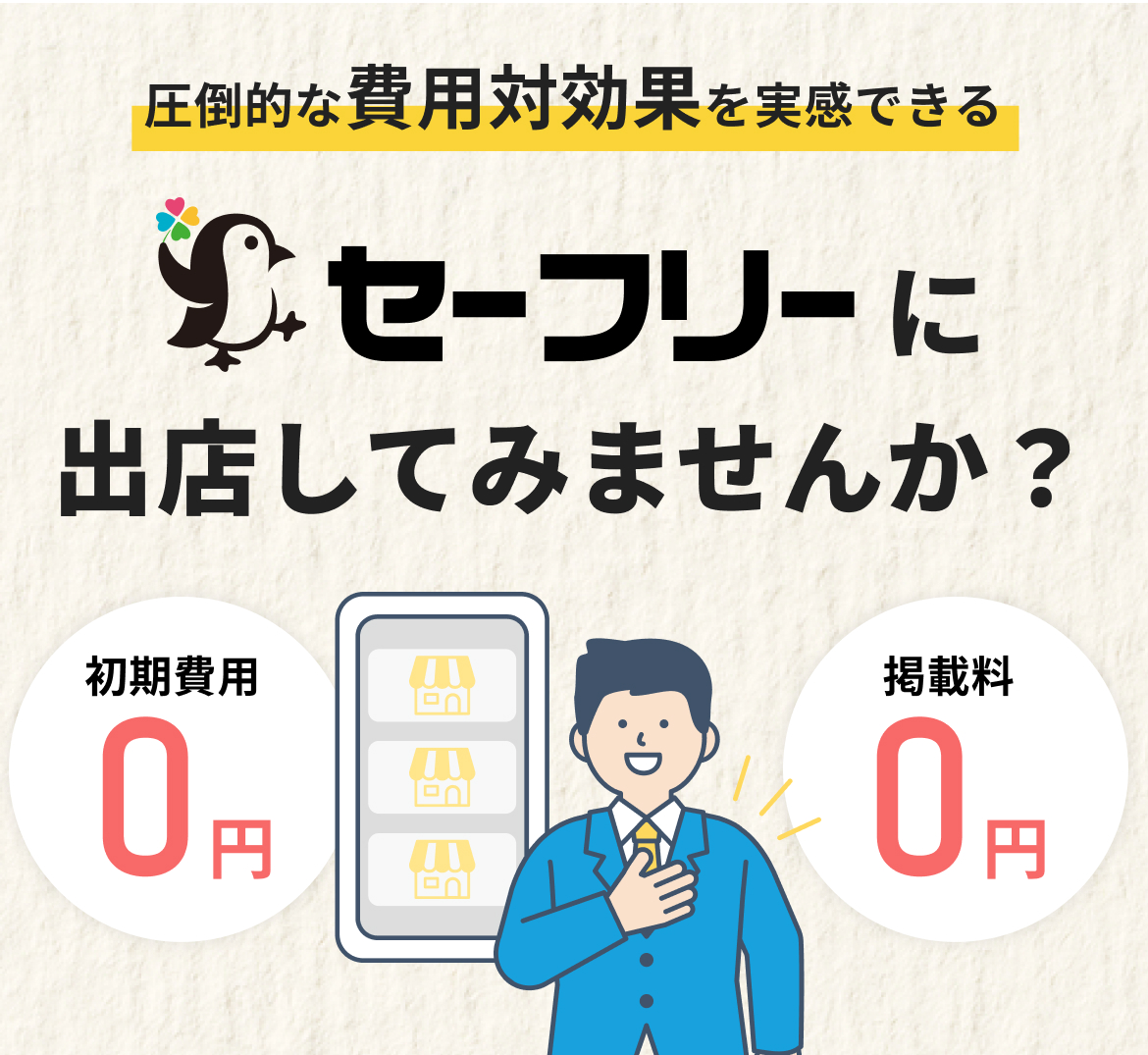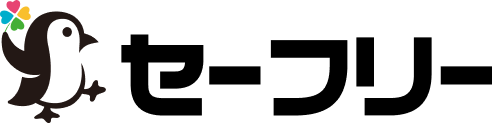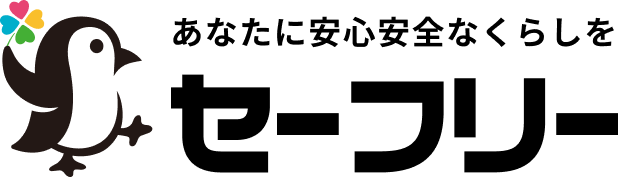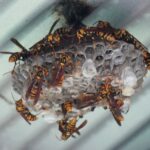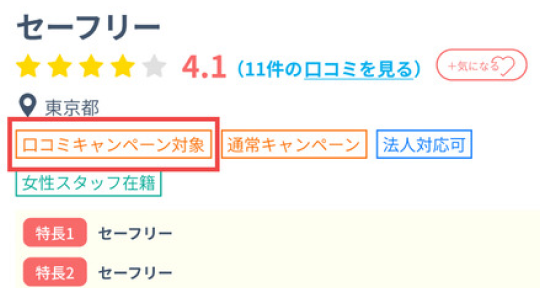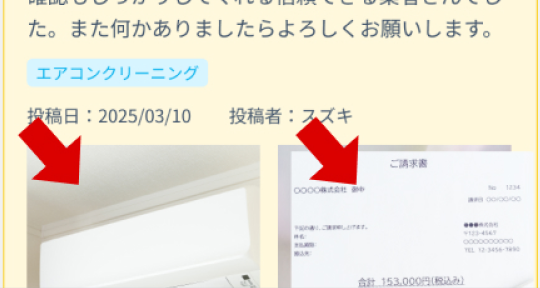2024.12.24 2025.03.01
本記事では、犬がぎんなんを食べてはいけない理由から食べてしまったときの対処法、日ごろから実践できる予防法までを詳しく解説します。
犬が食べてはいけないものにはいくつかあり、そのなかにぎんなんも含まれるので危険性を理解しておくことが大事です。
愛犬の身を守るため、ぎんなんについての知識をしっかり得ておきましょう。
ぎんなんが犬にどのような影響を与えるのかを知り、日常生活においても注意してみてください。
目次
犬がぎんなんを食べてはいけない理由

犬がぎんなんを食べてはいけない理由には、以下の3点が挙げられます。
- 中毒成分が含まれている
- 殻ごと食べて消化不良を起こす場合がある
- 外種皮に触れることで炎症が起きる場合がある
ぎんなんの特徴や配合されている成分に注意が必要なのがわかります。
それぞれの理由について、さらに詳しく記載するのでチェックしてみてください。
中毒成分が含まれている
犬にとってぎんなんが良くないのは、メチルピリドキシン(ギンコトキシン)という中毒症状を引き起こす可能性のある成分が含まれているためです。
メチルピリドキシンはビタミンB6を阻害する作用があります。
ビタミンB6は神経伝達物質を生成するのに必要な補酵素であるため、これによって様々な症状が引き起こされる場合があるのです。
殻ごと食べて消化不良を起こす場合がある
ぎんなんには殻が付いており、この殻ごと犬が食べてしまうことで消化不良を起こす場合があります。
特に、道に落ちているぎんなんには殻が付いているので、散歩のときに食べると危険です。
消化不良を起こし、体調不良が現れる可能性があります。
ぎんなんは、私たちが食べる部分だけでなく殻ごと食べるのも犬にとっては危険なのです。
外種皮に触れることで炎症が起きる場合がある
ぎんなんには、外種皮といって柔らかい部分があります。
この部分に犬が触れることで、炎症を引き起こす恐れもあるのでぎんなんは犬にとって危険なものなのです。
外種皮に手足や口などが触れると、皮膚に炎症が現れる場合があります。
ぎんなんは、食べるのはもちろん触れることも犬にとって避けなければならない行為なのです。
犬がぎんなんを食べて中毒を起こす摂取量

犬がぎんなんを食べてはいけない理由には、含まれている成分や殻、外種皮などが関係しています。
では、犬がぎんなんを食べて中毒を起こす摂取量はどれくらいなのでしょうか?
食べさせないのにこしたことはありませんが、どれくらいの量で中毒を引き起こす可能性があるのかを確認しておきましょう。
人間の場合、ぎんなんで中毒を起こすのはほとんど子どもであり、その目安は40粒程度といわれています。
何十粒という大量のぎんなんを食べたときに、中毒症状が起きると考えられるのです。
犬に関しては、人間よりさらに少ない摂取量でも中毒症状を招くリスクがあるので、少量であっても注意が必要です。
何粒なら大丈夫というのではなく、極力犬に与えないようにすることが重要です。
犬がぎんなんを食べてしまったときに起こり得る中毒症状

犬がぎんなんを食べると、わずかな量であっても中毒症状を起こす可能性があります。
具体的には以下のような中毒症状が起こり得るので、愛犬に異変がみられたら冷静かつ迅速に対処しましょう。
- 下痢
- 嘔吐
- 痙攣
- めまい
- 呼吸困難
- 下肢の麻痺
中毒症状は、ぎんなんを食べてからおよそ1時間~12時間で現れることが多いです。
特にぎんなんを噛み砕いて飲み込んでしまったような場合は、愛犬の様子をよく見て中毒症状が起きていないか確認してください。
※他にも犬が食べてはいけないナッツ類があるのでご確認ください。
さらに詳しく知りたい方はこちら
2024.11.26 2025.03.19
犬がぎんなんを食べてしまったときの対処法

犬がぎんなんを食べてしまったときは、状況に応じて速やかに対処して状況が悪化するのを防いでください。
ぎんなんを食べたときの対処法として、以下の3点を解説します。
- 飲み込む前なら口から出させる
- かかりつけの動物病院に相談する
- 休診や夜間の時は往診を検討する
それぞれの対処法についてよく確認し、愛犬の身を守れるようにしてください。
飲み込む前なら口から出させる
ぎんなんを口にしたのを見た、まだ飲み込んでおらず咀嚼している状態であれば、口の中から出させてください。
口から出すように言っても出せないときは、飼い主さんが口の中に手を入れてぎんなんを取り出します。
わずかなかけらであっても犬の体内に入れないことが大事なので、気づいたときにすぐ対処するのがポイントです。
かかりつけの動物病院に相談する
すでに犬がぎんなんを飲み込んでしまった、中毒症状が起きているような場合はすぐにかかりつけの動物病院に相談してください。
ぎんなんをどれくらい食べたのか、どのような症状が現れているかを細かく伝えて、指示を仰ぎましょう。
動物病院に相談する際は、犬がかじったぎんなんを保管しておき、食べた量や食べた時間を記録しておくのも忘れないでください。
休診や夜間の時は往診を検討する
犬がぎんなんを食べてしまったときは、できるだけ早く動物病院に相談するべきです。
しかし、犬がぎんなんを食べたタイミングや体調不良が現れたときが動物病院の診察時間外である夜や早朝の場合もあります。
またかかりつけの動物病院が休診の場合もあるため、そのようなときは夜間に対応しているところや往診可能な動物病院に相談してください。
自宅のある範囲からペットの救急センターについても調べておくと、万が一のときに駆け込める場合があります。
往診については設備などに限界がある点から、簡易的な治療になる可能性が高いです。
後日必ず動物病院に連れていき、詳しい診察を受けるようにしてください。
犬が銀杏を食べた時のNG対処法

犬がぎんなんを食べてしまったとき、つい慌ててしまう飼い主さんが多いでしょう。
しかし、愛犬が危険な物を食べてしまったときこそ、落ち着いて対処することが求められます。
たとえば以下に挙げるような行動は犬がぎんなんを食べたときのNG対処法となるので、避けるようにしてください。
- 無理やり吐かせる
- 動物病院に相談しないまま様子見する
2つのNG対処法について、詳細を確認しておきましょう。
無理やり吐かせる
犬がぎんなんを食べたとき、まだ飲み込んでいない状態なら口の中に手を入れて出す方法があります。
しかし、すでに飲み込んでしまった場合は、無理やり吐かせないようにしてください。
動物医療の専門家でない限り、無理に吐かせる行為は犬の身体に悪影響を及ぼす恐れがあります。
飲み込んでしまったときは動物病院に相談して、診察を受けてください。
動物病院に相談しないまま様子見する
犬がぎんなんを食べてしまったけれど中毒症状が現れていない、元気そうにしているからといって、そのまま様子見するのはやめましょう。
症状が現れていなくても、ぎんなんを食べたのが事実であるなら動物病院に必ず相談してください。
状況を正確に伝えて、愛犬の身体の状態をしっかり診てもらうことが大切です。
動物病院に相談しないまま様子見をするのは、飼い主さんにとっても不安が尽きません。
少しでも早く動物病院で診察を受けて、安心できるようにしましょう。
犬がぎんなんを食べてしまわないよう対策を

ぎんなんは、犬にとって危険な食べ物の一つです。
飼い主としては、そのような危険な食べ物が犬の口に入ってしまわないよう日ごろから気を付けておかなければなりません。
ぎんなんは身近なものでもあるので、次の点に注意しながら過ごしてみてください。
- 散歩コースに気を付ける
- 犬の手の届かないところに保管する
対策法について、詳しくみていきます。
散歩コースに気を付ける
秋になると、散歩コースに銀杏並木があるというケースがあります。
黄色く色づいた銀杏はとてもきれいですが、犬が下に落ちているぎんなんを食べてしまう恐れがあるので注意が必要です。
うっかり拾い食いする可能性があるので、ぎんなんが落ちている時期は銀杏のない散歩コースを選択してみてください。
散歩コースを変更するだけでも、犬がぎんなんを食べるのを防げます。
いつもと違う散歩コースを歩くのも犬にとって刺激になるはずなので、秋は銀杏並木を避けたコースを散歩するのがおすすめです。
犬の手の届かないところに保管する
ぎんなんは、散歩コースの銀杏並木だけでなく自宅においても誤食してしまう場合があります。
人間が食べようとぎんなんを保管していたり、食卓に並べているようなとき、気づかないうちに犬が食べてしまうことがあるので、家の中でも対策をとっておくことが大事です。
犬の手の届かないところに保管し、うっかり食べてしまうのを防いでください。
予想外に手が届いたり、保管場所から落ちるなどのトラブルも起こり得るので、日ごろからぎんなんの保管状態は確認しておきたいです。
犬にぎんなんはNG!万が一食べてしまったときは動物病院へ
犬にぎんなんを食べさせてはいけない理由から起こり得る中毒症状、食べてしまったときの対処法などをご紹介しました。
秋になると身近な存在にもなるぎんなんなので、散歩コースや自宅での保管方法などにも気を付けて愛犬が誤食するのを防ぐようにしましょう。
急なトラブルで動物病院を調べなければならないときは、「calooペット」がおすすめです。
- 犬の問題行動に対処できない
- しつけ方がわからない
- しつける時間がない